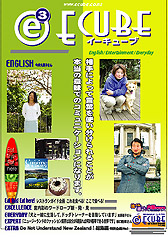ニュージーランド・ジャパン・ソサエティー・オークランド代表:今井 久美子 さん
 相手によって言葉を使い分けられることが本当の意味でのコミュニケーションになります。
相手によって言葉を使い分けられることが本当の意味でのコミュニケーションになります。
ワーキングホリデーや学生として英語を習得するために海外に出る人は多いが、限られた時間の中で英語力が伸びても日本に帰国して、そのレベルを維持することは容易ではない。幼いころにニュージーランドに来て英語を勉強し始め、帰国子女として日本に帰国してからも継続して英語を勉強していた久美子さんはそのレベルを維持するための環境作りに成功している一つの例だと言える。幼い頃に海外で育ったにもかかわらず、日本語、英語ともに堪能な彼女は今でも言葉を正しく使えるように心がけていると言う。それは、コンピューターなどの伝達技術の発達により、情報が速く、正確に得られるようになっても「普段から日本人は着物を着て過ごしている」などの誤った情報が往来しているため、海外で生活する日本人として、その国の人達に自国の文化や風習を正しく伝えていくためには言葉を適切に使いこなすことが重要だと考えるからだ。
今井 久美子
Kumiko Imai
New Zealand Japan Society of Auckland
Vice President
神戸海星女子学院大学英文科卒業。12歳の時に初めてニュージーランドに来る。高校、大学は日本で過ごすが、その後しばらくして、再びニュージーランドで生活することとなる。テキスタイルエージェントとして生地などの輸出入を行う会社Tradelink Export / Import Ltdを営むかたわら、ニュージーランド・ジャパン・ソサエティー・オークランドでの文化活動にも積極的に取り組んでいる。最近はOpen Polytec Applied Scienceを受講している学生としても忙しい毎日を過ごしている。
英語への興味
私の父は私が幼い頃から仕事の関係で海外によく出かけていました。1年の3ヶ月ぐらいしか日本にはいませんでした。また、祖父も海外や英語とのつながりが深く、通訳として会社で働いていたそうです。祖父の頃には英語のテキストがなかったため、聖書を使って教会の宣教師から助けてもらいながら、ほとんど独学で英語を学んでいったそうです。祖父の勉強方法で辞書のページを覚えると破いて、そのページを食べるというものがありました。初めは冗談だと思っていたのですが本当に彼が持っていた辞書はとても薄くぺらぺらだったのを覚えています。
また、私の家ではテストがありました。常識テストと題して父が先生役をして国連加盟国は?とか、先日父が行って来た国はどこ?と地球儀を使って国の場所を示すなどのテストをしていました。また、読書の時間をもうけて家族全員で本を読んで感想文を書いて発表したりもしました。祖父に順番に読んでもらったグリム童話やジョン万次郎についての話はとても好きで自然と海外への興味を持つようになりました。
日本語を勉強している外国人をホームステイとして受け入れたのもその頃です。私は歌謡曲を一緒に歌いながら意味を教え、彼女には父が海外で購入してきてくれた英語の絵本を読んでもらうといったエクスチェンジをしていました。歌謡曲の歌詞の意味がわからず相手にうまく意味を伝えられなかったこともありましたが他のクラスメートには体験できないことをしている自分に満足していました。
また、その頃から「英語を勉強すると世界が広がる」ということを何となく感じていったと思います。
当初の英語
父の転勤で12歳の時にニュージーランドのオークランドに来ることになりました。12月という時期に来たことでニュージーランドの学校が長いホリデー期間に入っていました。
家族全員、初めての海外ということもあり、全く何もわからない状態でした。言葉はもちろん、この国の人達がどんな考えを持っているかもです。洗濯物を干していて雨が降ってきたときでした。取り込もうと急いで外に出て、かごに入れていたら近所の人がやってきて、いつかは乾くからと、かごに入れた洗濯物をまた干し直されたことがありました。また、毎日掃除機をかけていたらカーペットがすり減るからやめなさいと言われたりもしました。少しずつわかっていくニュージーランドの人達の考えを通して、日本との違いを感じました。
それから学校が始まったのですが、日本で英語を習ったことがない私は授業でも普段でも言いたいことが言えませんでした。何か困ったことがあるとすでに学校に通っていた年下の日本人の子を呼び、通訳になってもらっていました。また、学校で英語を特訓するためのクラスを設けてくれたのですが、授業に出るのがいやでしょっちゅう脱走していました。親にそのことがバレて怒られました。
その後、英語を特訓するクラスに一緒にいた子が英語を上達させて次々といなくなりました。私は一人取り残されていくさびしさからホームシックにもなりました。当時の私は英語を間違うことがとても恥ずかしかったのです。
習得方法1
通訳として私の言いたいことを代弁していた子が日本に帰国することになりました。僕が帰ったら今井さんは困るのでは?と心配され、このままでは大変だと思いました。ですが英語を間違うことが恥ずかしく、そんな状況になっても話す勇気を持てませんでした。
あるとき昼食にお弁当を持ってきていた私にクラスメイトが「それは何だ?」と中身を聞いてきました。のりを指さしていたので辞書で調べてseaweedだとわかりました。ですがどう発音していいかわからない私は辞書を見せて、これと指さしました。それを見るなり、クラスメイトはyuckと言いました。すぐに何と言ったのか、単語の意味を辞書で調べましたが載っていませんでした。
家に帰って、父にその単語の意味を聞くと気持ち悪いということを知りました。また、俗語だから私の持っていた辞書には載っていないこともわかりました。
英語を話すことに抵抗はあったのですが毎日の生活の中で見聞きする言葉を辞書で調べたり、辞書で調べても載っていないものは父に聞いて意味を覚えていきました。
少しずつボキャブラリーが増やせたことから次に書くことで気持ちを相手に伝えようと思いました。文法をそれまで習ったことがない私は日本語の文法と英語の文法が異なることを知りませんでした。だから、ただ日本語と同じように日本語を英語の単語に置き換えれば英語の文章になると信じていたのです。
例えば、「私は英語を勉強する」という簡単な文章を英語に置き換え、「I English study」のようにしていたのです。みんなに気持ちが伝えられると思い、早速先生に見てもらいました。ですが先生は首を傾げて困った顔をして、何もいわずに添削してノートを返しました。
何が間違っているか先生から説明されても英語がわかりません。私は添削されたノートを頼りに自分で理解していくしかありませんでした。文章を作り、添削してもらうことを繰り返すことで日本語と英語は逆さまなんだといつしか気づきました。そして、先生から合格をもらえる文章を作れるようになりました。
英語を習っている人は機会があればネイティブスピーカーに作った文章を見てもらうといいと思います。彼らに見てもらうことによって文法はもちろんのことですが相手に伝えたいニュアンスやインパクトを与えられる言い回しが入った文章についても勉強できるからです。
習得方法2
ニュージーランドに来て1年ほど経った頃だったと思います。なかなか英語が上達しないことで両親が家庭教師を雇うことにしたのです。その人はニュージーランドで初めて外国人に英語を教える資格を持った人で、今の時代にはいませんがスパルタ式の先生でした。同じ間違いを3回するとたたくほど厳しい人でした。
課題には新聞の中のわからない単語に印を付けて意味を調べることがありました。ですが、日本語で書かれた新聞でもわからないような内容だというのに英語で書かれた新聞ですから印だらけになってしまいました。
また、日本からニュージーランドに戻ってきた日本語が話せるキウィのクラスメイトと友達になりました。彼は英語を間違えることは恥ずかしくないと言ってくれました。 それから英語を話すことに対しての怖さが消え、安心して話せるようになりました。そして次第に友達も増えていったのですが時折、相手にわかってもらえないときがありました。それは発音の問題でした。特にLとRの発音は苦労しました。友達にLeeとHarrietという名前の子がいたのですが名前を呼んでもわかってもらえないのです。
発音の違いがわからず、なぜ相手に言葉が伝わらないか理解できなかった私に彼らはその原因を突き止め、教えてくれました。そして、LやRを含む単語を彼らが発音して私が同じようにまねる訓練が始まりました。
そういったことから時間はかかりましたが、友人や先生の助けもあり、英語に慣れていったのです。
英語のレベル継続
ニュージーランドには16歳までいて、その後、日本に戻って高校に進学しました。帰国子女のためのクラスに入学しました。英語だけでなくフランス語を使っていた人や数ヶ月しか滞在していない人、海外で生まれた人などがいました。
高校では語学レベルが違うという理由から同じくクラスでも英語の授業は3つのクラスに分かれて勉強していました。大学では英文科に入り、英語検定を受けたり、教員免許を取得したりもしました。ですが、海外にいたときと環境を同じにすることは大変難しいと感じました。極端に英語を使う機会が減っていたのです。
ニュージーランドにいずれ戻ることを考えていた私は英語に触れる時間を自分で作るように心がけました。本屋で大量のペーパーバックを購入して英語の活字に触れるようにしたり、NHKで放送している英語講座を見てリスニングにも力を注いでいました。
帰国子女の友達と会うときは日本語でなくお互いに英語で会話するようにしました。また、英語を使う場を探し、いろいろな場に顔を出すようにしていました。大学で英語に自信のある人が参加している英語でのディベートに興味を持ち、参加したのもそのためです。外国人が集まるパーティやパブなどにも行きました。
英語を使っての文化交流
大学卒業後は、日本でアパレル関係の仕事に就き、5年ほど働いていましたが、29歳の時にニュージーランドに戻ってきました。
しばらくして、ニュージーランド・ジャパン・ソサエティー・オークランド支部に参加することにしたのです。
この国でキウイ達に助けてもらった経験から何か「恩返し」をしたいと思っていたのです。大学時代の大学祭運営実行委員会の経験がこんな所で生きるとは思いませんでした。
ニュージーランド・ジャパン・ソサエティー・オークランド支部は1960年に創立された「日本とニュージーランド両国の親睦と相互理解を深めること」を目的とするボランティア組織です。私はそこで日本文化についての理解を深めるイベントの開催や文化交流促進のために主催者との打ち合わせ、スケジュール調整などの幅広い仕事を行っています。
活動の内容には、毎月第1、第3水曜日にオークランド・カレッジ・オブ・エデュケーションで夜7時30分から行われている英語、日本語の会話を楽しんでいただく「会話の夕べ」や年4回開かれる社交、文化交流の行事である「クラブナイト」。また、会員、関連団体の方々に2ヶ月毎に会報誌「集い」を発行したり、盆栽、生け花、折り紙、お茶の作法、着物の着付け、日本の芸術作品の展示などで日本を紹介する「日本文化祭り」といったイベントの実施。
その他7年前にフランクス・バターフィンガーズというソフトボールチームを結成しました。高知のよさこい祭りの「よさこい」に北海道の漁師の歌「ソーラン節」をアレンジして誕生した「よさこいソーラン」をニュージーランドに紹介するプロジェクトHaere舞などの活動も1年前から行っています。
ニュージーランドで行われるイベントへの参加は日本の文化を紹介することを意味します。場所によっては、首相や教育大臣に会う機会もあります。 そこでは日本人としてのニュージーランドの貢献が問われ、相手に日本をよく理解してもらうためのスポークスマンとしての役割が大半を占めます。ですから、事前に相手がどのような人か知るために情報収集して相手にあった話題を準備しておくことも多いのです。日頃から新聞やテレビを見てニュージーランドと日本両国の動きを知っておくことがとても大切なのです。
会った後には、相手にいい印象を残すために手紙を送ったりするなどのフォローアップも重要なことだと思います。
ニュージーランドに戻ってきた当初、ビジネスではありましたが、カジュアルな格好をした若い世代の人に会う機会がありました。私はスーツで出向き、相手をかしこまらせてしまうということがありました。そこで次に会うときには少しラフな格好をして行ったところ、前回とは違ってスラングが会話で出るほど、リラックスしてお互い話す事が出来ました。
英語を学んでいる人でスラングだけでコミュニケーションを取ろうとする人がいますが相手は基本の英語力があるということを忘れてはいけないと思います。それだけではとても危険だと思うのです。時と場合によって相手に合わせた接し方、言葉の使い方は必要です。同じ言葉を使っていても誤解が生じたりします。ですから、この国の多くの人に日本を知ってもらうには、適切な言葉の使い方があってはじめて正しく伝えられると思うのです。
私は今後も日本人会、在オークランド日本総領事館、オークランド市役所、オークランド・カレッジ・オブ・エデュケーションなどの団体との様々な活動を通して日本を紹介していきたいと思います。
久美子さんの英語上達のポイント
- 「一生の恥より1回の恥」だと思って間違いを恐れず、作った文章はネイティブスピーカーにチェックしてもらう。
- LやRを含む単語をネイティブスピーカーに発音してもらい、同じようにまねる。
- ペーパーバック、NHKで放送している英語講座、外国人が集まるパーティやパブなど身近にある英語に触れる環境を最大限に利用する。
- スラングなどの言葉は基本が出来てから会話に幅を持たせるために覚える。